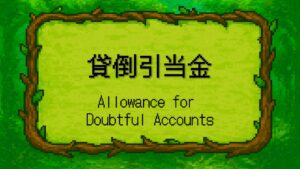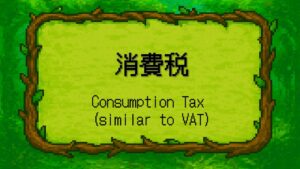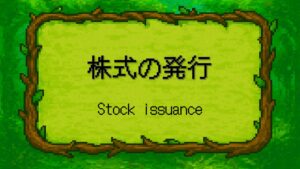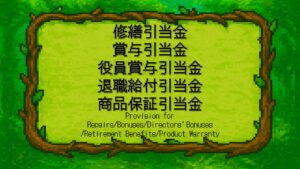はじめに
この記事では、以下の6つの項目を復習・整理することを目標にしています。
①有価証券の概要
②売買目的有価証券の期中・期末仕訳について
③満期保有目的債券の期中・期末仕訳について
④子会社株式および関連会社株式の期中・期末仕訳について
⑤その他有価証券の期中・期末仕訳について
⑥手数料・端数利息・財務諸表上の表示について
それでは、よろしくお願いします。(※使用教材の第11章「有価証券」を参考に作成しています。)
有価証券
#有価証券とは
有価証券とは、「金銭的価値のある証券」のことで、株式(昔でいう株券)、債券(国債・社債など)、投資信託(2級ではあまり出題されない)のことを指します。有価証券は、その購入目的(何の目的で購入するか)によって、4つに大きく分類され、それぞれで勘定科目や会計処理が異なります。
有価証券の分類と概要
| 分類 | 取得目的 | 評価方法 | 決算処理 | 株式 | 債券 |
| 売買目的有価証券 | 売買による利益獲得 | 時価評価 | 評価損益は 損益計算書に計上 | 〇 | 〇 |
| 満期保有目的債券 | 満期まで保有し利息を得る | 償却原価法※ (時価評価しない) | 利息収益計上 原則として時価評価なし | × | 〇 |
| 子会社株式および関連会社株式 | 他社を支配・影響力確保 | 取得原価法 | 原則として時価評価なし | 〇 | × |
| その他有価証券 | 安定収益・関係強化など | (時価が存在すれば) 時価評価 | 評価差額は 純資産に計上 | 〇 | 〇 |
時価評価について
「時価」とは「市場参加者が自由に取引できる状況で、合理的かつ客観的に形成された市場取引価格」=「市場価格」を指します。
「時価評価」とは、保有している資産や負債について、「決算時点(期末時点)の市場価格(時価)を基準として価値を再評価すること」を指します。
時価評価が適用される要件としては、
①市場価格が客観的かつ公正に形成されていること(十分に整備された取引市場が存在し、取引価格が容易かつ客観的に確認できること)
②売却可能性・換金性が高いこと(保有している資産が、容易かつ迅速に市場で売却(換金)可能であること)
③評価差額の重要性(時価評価により発生する評価差額(含み損益)が財務諸表利用者の判断に重要な影響を与えること)
を満たす必要があります。
その他の評価方法との比較
| 評価方法 | 評価基準 | 損益反映のタイミング |
| 時価評価法 | 期末時点の市場価格 | 評価時点(未実現利益・損失も反映) |
| 取得原価法 | 資産取得時の購入価額(原価) | 売却・処分時のみ損益に反映 |
| 償却原価法 | 当初取得価額から満期までの期間で償却 | 償却費として毎期少しずつ損益に反映 |
有価証券の簿価について
同一銘柄を複数回に分けて購入した場合は、平均法(移動平均法と総平均法のいずれか)で、簿価を算出します。平均法の考え方については こちらのページを参照してください
※税金や証券会社の手数料などは除外してます。
#売買目的有価証券の仕訳
期中仕訳
例1:株式の場合
・9月1日、A株式会社の株式を、売買目的で10株(@100円)購入した。
| 借方 | 貸方 |
| 売買目的有価証券 1,000円 | 現金 1,000円 |
・9月30日、A株式会社の株式が120円に値上がりしたので、10株売却した。
| 借方 | 貸方 |
| 現金 1,200円 | 売買目的有価証券 1,000円 |
| 有価証券売却益 200円 |
例2:債券の場合
・売買目的で、額面1,000,000円の社債を、@97円(社債100円につき3%引きの97円)で現金購入した。
| 借方 | 貸方 |
| 売買目的有価証券 970,000円 | 現金 970,000円 |
・配当金領収書10円を受け取った。(債権を保有していると配当金を貰える場合がある。)
| 借方 | 貸方 |
| 現金 10円 | 受取配当金 10円 |
・利払日に利息10円を現金で受け取った。(債権を保有していると利息が貰える。)
| 借方 | 貸方 |
| 現金 10円 | 有価証券利息 (受取利息) 10円 |
期末仕訳
売買することで利益を得ることを目的にしているため、時価に評価替えをします。
例:25年9月1日、A株式会社の株式を、売買目的で10株(@100円)購入した。(A社株式の簿価が1,000円)
・9月1日
| 借方 | 貸方 |
| 売買目的有価証券 1,000円 | 現金 1,000円 |
・パターン①:26年3月31日、A社の株式の終値(=時価)が130円の場合
| 借方 | 貸方 |
| 売買目的有価証券 300円 | 有価証券評価益 300円 |
・パターン②:26年3月31日、A社の株式の終値(=時価)が80円の場合
| 借方 | 貸方 |
| 有価証券評価損 200円 | 売買目的有価証券 200円 |
翌期首仕訳
・パターンA:切放方式(前期末時価をそのまま簿価にする)
仕訳なし
・パターンB:洗替方式(時価評価前の帳簿価額に戻す)
※時価評価替えパターン①の場合
| 借方 | 貸方 |
| 有価証券評価益 300円 | 売買目的有価証券 300円 |
#満期保有目的債券の仕訳
例1:25年4月1日、A社は満期まで保有する目的でB社社債(額面1,000,000円、25年4月1日発行、満期5年、利払日3月31日、年利2%)を、@95円で現金購入した場合
期中仕訳
| 借方 | 貸方 |
| 満期保有目的債権 950,000円 | 現金 950,000円 |
期末仕訳
満期まで保有をすることで儲けることが目的であるため、時価があっても時価評価は行いません。時価評価は行いませんが、金利の調整であると判断された場合には、償却原価法という方法で評価します。(償却原価法には利息法と定額法がありますが、簿記2級では定額法を学習します。金利の調整かどうかを判断する問題はでません。)
償却原価法では、満期日までの期間にわたって利息収益を計上していく必要があります。借方は「満期保有目的債権」、貸方は「有価証券利息」を使用します。上記の例だと、5年で、50,000円の利息収入を計上することになるので、毎年以下のように仕訳を行います。以後、この満期保有目的債権の簿価を増やす仕訳を償還期日まで繰り返します。
| 借方 | 貸方 |
| 満期保有目的債権 10,000円 | 有価証券利息 10,000円 |
また、利払日が3月31日であるので、上記の仕訳とは別に以下の仕訳も行います。
| 借方 | 貸方 |
| 現金預金 20,000円 | 有価証券利息 20,000円 |
債券取引の基本の流れ
①A社がB社の満期5年の社債を発行価額で購入(B社がA社に借金)
②毎年、A社はクーポンレート(表面利率)分の利息を受け取る
③5年後に、A社はB社から額面金額で返済を受ける(この返済を「償還」、額面金額を「償還金額」とよぶ)
つまり、A社は
(1)毎年の利息
(2)償還価額と発行価額との差
の2つが儲けになります。
金利の調整について
・クーポンレートを高く設定→発行価額と償還価額の差を小さく設定
・クーポンレートを低く設定→発行価額と償還価額の差を大きく設定
このように、クーポンレート(表面利率)の高低を、発行価額と償還価額の差の大小で調整することを「金利の調整」とよびます。
償却原価法について
償却原価法は、取得価額と額面金額との間に差額があり、なおかつその差額が金利の調整と認められる場合にのみ行われる会計処理(利息調整)のことです。
償却原価法は、時価評価ではありません。加算した後の数値が新たな帳簿価額であり、償却原価法により時価に評価替えしているのではありません。
時価評価と償却原価法のどちらも、期末日に計算後の数値を貸借対照表に記載するという点では共通ですが(していることは似ているが)、理屈が全く違うので、注意してください。取得価額と額面金額が等しい場合や、差額があっても金利の調整と判断されない場合は、取得価額のまま貸借対照表に記載します。
例2:25年3月1日、A社は満期まで保有する目的でB社社債(額面100万円、25年3月1日発行、満期5年、利払日2月28日、クーポンレート年1.2%)を、@94円で現金購入した。額面と購入金額との差額は金利の調整差額であると認められる場合
25年3月1日
| 借方 | 貸方 |
| 満期保有目的債権 940,000円 | 現金預金 940,000円 |
25年3月31日
①償却原価法(60ヶ月で60,000円の増加=1カ月あたり1,000円の増加)
| 借方 | 貸方 |
| 満期保有目的債権 1,000円 | 有価証券利息 1,000円 |
②利払日と決算日が異なるので、利息の未収計上
| 借方 | 貸方 |
| 未収有価証券利息 1,000円 | 有価証券利息 1,000円 |
25年4月1日(再振替仕訳)
| 借方 | 貸方 |
| 有価証券利息 1,000円 | 未収有価証券利息 1,000円 |
26年2月28日
| 借方 | 貸方 |
| 現金預金 12,000円 | 有価証券利息 12,000円 |
26年3月31日
| 借方 | 貸方 |
| 満期保有目的債権 12,000円 | 有価証券利息 12,000円 |
| 未収有価証券利息 1,000円 | 有価証券利息 1,000円 |
#子会社株式及び関連会社株式の仕訳
子会社株式、関連会社株式かどうかを判別する基準は、「形式基準(持株比率)」と支配・影響の実態もした実質基準があり、現在は実務上では「実質基準」により判別しています。以下、一覧表にまとめています。
| 種類 | 形式基準 (持株比率) | 実質基準 |
| 子会社株式 | 50%超 | 形式基準に加え、40%以上50%以下であっても、 多数の役員派遣など意思決定を支配している場合 |
| 関連会社株式 | 20%以上 50%以下 | 形式基準に加え、子会社に該当せず、15%以上で代表取締役を派遣しているなど重要な影響を与えている場合 |
| 売買目的有価証券 その他有価証券 | 20%未満 | 形式基準に加えて、関連会社株式ではない株式 |
例:C社の発行株式10万株の内3万株を一株1,000円で購入した。代金は当座預金から支払う場合
期中仕訳
| 借方 | 貸方 |
| 関連会社株式 30,000,000円 | 当座預金 30,000,000円 |
期末仕訳
仕訳なし
支配すること・影響力を持つことが保有する目的で、売却することを予定していないから、(時価があっても)時価評価はしません。
#その他有価証券の仕訳
その他有価証券とは
その他有価証券とは、上記の3つのカテゴリーのどれにも属さない有価証券のことです。
例えば、
・長期利殖目的(資産を長い期間もって「配当・利子・値上がり」で殖やすこと)で取得
・取引先との関係維持のために取得(=政策保有・持ち合い)
・余裕資金の安全運用として取得
・配当(利息)収入の獲得を主目的として取得 など
会計処理の考え方
「株式」の場合は、時価が存在している場合には期末に時価評価はしますが、時価と帳簿価額との差額を損益計上しません。(時価が存在しない場合は、当然時価評価しません。)
「債券」の場合は、満期保有目的債権と同様に条件を満たせば、償却原価法で帳簿価額を計算します。また、時価があれば、時価評価を行いますが、損益計上はしません。
「時価評価の方法」は、全部純資産直入法(評価損益は損益計算書に反映させない)と部分純資産直入法(プラス評価の時は損益計算書に反映させないが、マイナス評価の時は損を計上する)の2つがあります。原則法は「全部純資産直入法」です。(簿記2級の範囲も全部純資産直入法です。)
| 区分 | 時価評価 | 損益計上 | 償却原価法 |
| 株式 | (時価があれば)〇 | × | × |
| 債券 | (時価があれば)〇 | × | (条件満たせば)〇 |
例:25年7月1日、営業見合いでD社の株式1万株を、一株500円で購入した。代金は当座預金から支払う場合
期中仕訳
| 借方 | 貸方 |
| その他有価証券 5,000,000円 | 当座預金 5,000,000円 |
期末仕訳
例1:期末(26年3月31日)になり、D社の株価が一株700円になっていた場合
| 借方 | 貸方 |
| その他有価証券 2,000,000円 | その他有価証券評価差額金 2,000,000円 |
例2:期末(26年3月31日)になり、D社の株価が一株400円になっていた場合
| 借方 | 貸方 |
| その他有価証券評価差額金 1,000,000円 | その他有価証券 1,000,000円 |
「その他有価証券評価差額金」は純資産項目であり、収益項目ではありません。洗替法だけが認められているので、翌期首に再振替仕訳が必要です。
#購入・売却時の手数料
購入時
資産を購入した時に発生する不随費用は、取得原価に含めます。
・990,000円のA社株式を購入し、証券会社へ手数料10,000円とともに当座預金から支払う場合
| 借方 | 貸方 |
| 売買目的有価証券 1,000,000円 | 当座預金 1,000,000円 |
売却時
有価証券の売却で支払う仲介手数料は、特段の取り決めがなければ、売却した側が負担します。
①保有しているA社株式(簿価900,000円)を 1,000,000円で売却した。売却代金は証券会社の手数料10,000円が差し引かれた金額で当座預金に入金された場合(支払手数料を計上する場合)
| 借方 | 貸方 |
| 当座預金 990,000円 | 売買目的有価証券 900,000円 |
| 支払手数料 10,000円 | 有価証券売却益 100,000円 |
②保有している A社株式(簿価900,000円) を 1,000,000円で売却した。売却代金は証券会社の手数料10,000円が差し引かれた金額で当座預金に入金された場合(支払手数料を計上しない場合)
| 借方 | 貸方 |
| 当座預金 990,000円 | 売買目的有価証券 900,000円 |
| 有価証券売却益 90,000円 |
勘定科目
売買目的有価証券では、取引で発生した費用・収益を以下のように有価証券運用損/運用益としてまとめる場合もあります。
| 区分 | 勘定科目 | 備考 | |
費用 | 有価証券売却損 | 有価証券運用損 | 売却による損失 |
| 有価証券評価損 | 時価評価による減少分 | ||
| 有価証券利息 | 債券購入時の端数利息など | ||
| 売却手数料 | 売却時に発生する証券会社への手数料 | ||
収益 | 有価証券売却益 | 有価証券運用益 | 売却で発生した利益 |
| 有価証券評価益 | 時価評価による増加分 | ||
| 有価証券利息 | 債券の保有による利息収益 | ||
| 受取配当金 | 株式の保有による配当 | ||
#端数利息
端数利息とは
債権の保有期間に応じた日割りの利息のことで、購入側が売却側に支払う利息です。
「額面金額×年利率×保有日数÷365」の計算式で求めます。
保有日数は利払日の翌日からのカウントになります。
例えば、利払日:4/26、購入日:6/3の場合の保有日数は、38(4+31+3)日となります。
例:(A社がC社社債を売買目的で960,000円で購入後)B社に1,000,000円で売却して、端数利息が5,000円の場合
・A社仕訳(売却側)
| 借方 | 貸方 |
| 当座預金 1,005,000円 | 売買目的有価証券 960,000円 |
| 有価証券売却益 40,000円 | |
| 有価証券利息 5,000円 |
・B社仕訳(購入側)
| 借方 | 貸方 |
| 売買目的有価証券 1,000,000円 | 当座預金 1,005,000円 |
| 有価証券利息 5,000円 |
購入側は、次の利払日に保有する前からの期間分の利息を受け取れるため、端数利息を取得原価に含めてはいけません。
#財務諸表上の表示
B/S上
有価証券は正常営業循環外の勘定科目であり、1年基準で流動・固定を判定します。
| 区分 | 表示場所 | 表示名 |
| 売買目的有価証券 | 流動資産 | 有価証券 |
| ①満期日が1年以内 満期保有目的債券 | 流動資産 | 有価証券 |
| ②満期日が1年超 満期保有目的債券 | 固定資産 (投資その他の資産) | 投資有価証券 |
| 子会社株式・ 関連会社株式 | 固定資産 (投資その他の資産) | 関係会社株式 |
| ①株式 その他有価証券 | 固定資産 (投資その他の資産) | 投資有価証券 |
| ②満期日が1年以内 その他有価証券 | 流動資産 | 有価証券 |
| ②満期日が1年超 その他有価証券 | 固定資産 (投資その他の資産) | 投資有価証券 |
P/L上
売却損益の勘定科目
| 区分 | 表示場所 | 表示名 |
| 売買目的有価証券 | 営業外損益 | 有価証券売却損・ 有価証券売却益 |
| 満期保有目的債券 | 特別損益 | 投資有価証券売却損・ 投資有価証券売却益 |
| 子会社株式・ 関連会社株式 | 特別損益 | 関係会社株式売却損・ 関係会社株式売却益 |
| その他の有価証券 | 営業外損益 or特別損益 | 投資有価証券売却損・ 投資有価証券売却益 |
売却以外の損益の勘定科目
| 区分 | 表示場所 | 表示名 |
| 売買目的有価証券の 時価評価損益 | 営業外損益 | 有価証券評価損・ 有価証券評価益 |
| 債券を保有している と発生する利息 | 借方:営業外費用 貸方:営業外収益 | 有価証券利息 |
| 配当金 | 営業外収益 | 受取配当金 |
表示名は、あくまでP/L上に表示されるときの勘定科目名であり、仕訳で用いる勘定科目は異なる場合があるので注意すること。(問題文に指定ある場合はその勘定科目を使用すること。)
①「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画「有価証券①(総論)」
②「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画「有価証券②(4分類解説)」
③「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画「有価証券③(端数利息、表示)」
④「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画「有価証券④(時価評価)」
※初めての方は、こちらの記事から読んでいただけますと幸いです。