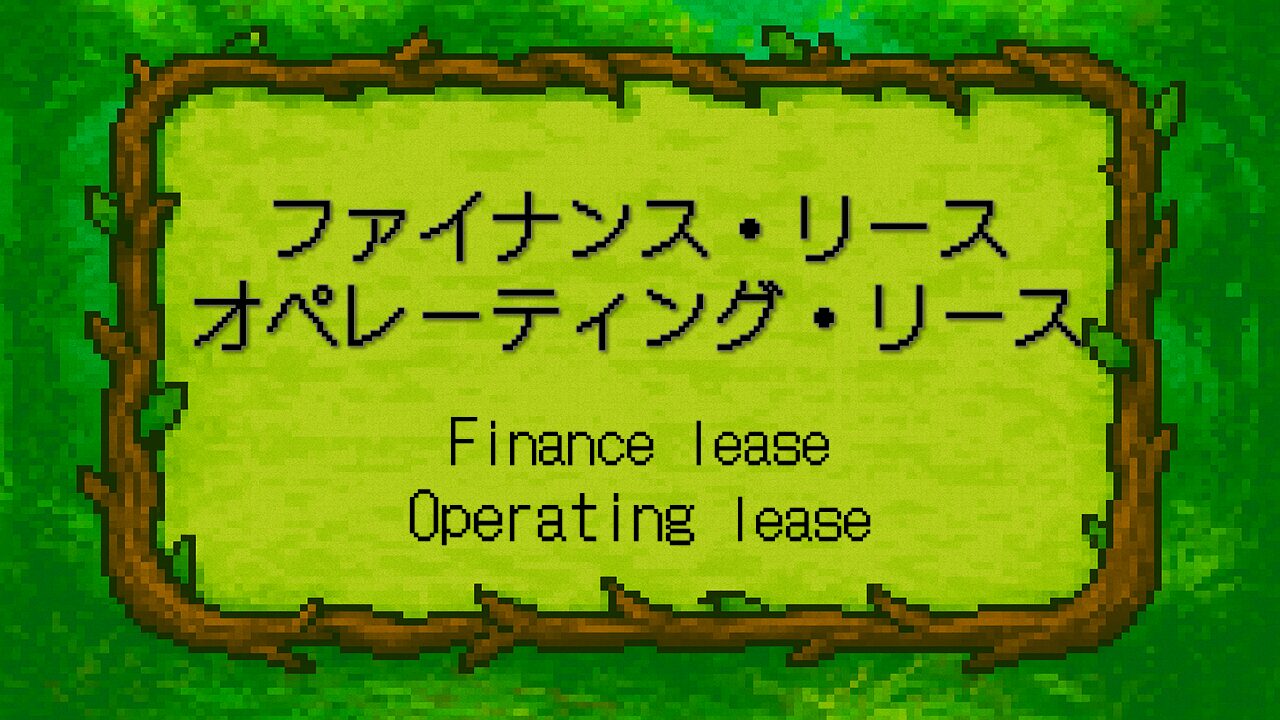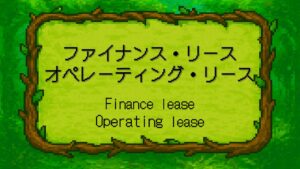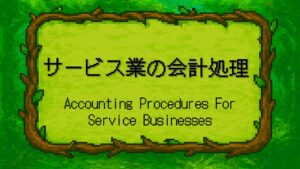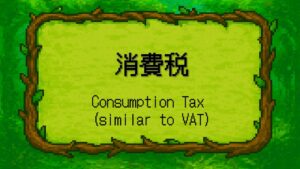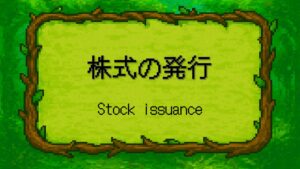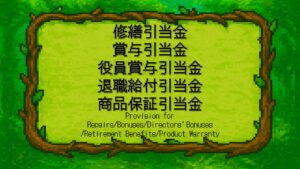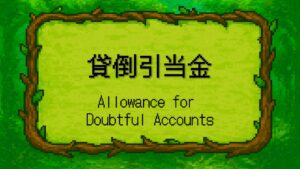はじめに
この記事では、以下の3つの項目を復習・整理することを目標にしています。
①リース契約の分類について
②オペレーティング・リース取引の(借主側)仕訳方法について
③ファイナンス・リース取引の(借主側)仕訳方法について
それでは、よろしくお願いします。(※使用教材の第8章「リース」を参考に作成しています。)
リース取引
#会計学上の「リース」とは
会計学上でのリースとは、民法上の賃貸借全て(有料での物の貸し借り全部、例えば、レンタル・チャーター・不動産賃貸など)を指します。また、リースは、「ファイナンス・リース」もしくは「オペレーティング・リース」のどちらかに分類されます。(賃貸借をどちらのリース取引に分類するかは、1級の範囲)
#「リース」の分類について
「ノンキャンセラブル」かつ「フルペイアウト」の条件を満たせば「ファイナンス・リース」となり、これに該当しなかった残りの賃貸借(リース)全てが、「オペレーティング・リース」に該当します。
(※2級では、どちらに該当するか判定させることはありません。)
ファイナンス・リースに該当するための条件
| 条件 | 内容 |
| ノンキャンセラブル | 中途解約不能(中途解約すると、残りのリース料を全額支払う条件など、事実上解約できないケースも含む) |
| フルペイアウト | リース物件を使用することにより得られる便益(経済的利益)の享受と、維持費などのリスク負担を、借主が担うこと。(リース料≒購入金額+維持費+利息) |
実務上のリースとは通常、ファイナンス・リースを指し、予め所有している物を貸すというよりは、借主に代わりに購入(立替)をし、その代金を分割で回収することが一般的です。(実質的には、お金を貸していることになるので、ファイナンス・リースと呼ばれます。)
#「オペレーティング・リース」の会計処理
オペレーティング・リースは「経費処理=費用処理」を行います。このように処理することを、会計上では「賃貸借処理」と呼びます。「支払リース料」の勘定科目で費用計上します。(※2級では、借主側の仕訳のみ)です。)
*仕訳の具体例
例1:資材運搬用に、レンタカー会社からトラックを1日借りて、レンタル料を10,000円を現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 |
| 支払リース料 10,000円 | 現金 10,000円 |
※オペレーティング・リースは、短期間だけではなく、3-5年など比較的長期間の場合もあります。
例2:25年4月1日に、リース会社と自動車のリース契約(リース期間3年、年間リース料120,000円、リース料の支払いは毎年3月31日に当座預金から振込、オペレーティング・リースに該当)の場合
・4月1日:
<仕訳なし>
・毎年3月31日:
| 借方 | 貸方 |
| 支払リース料 120,000円 | 当座預金 120,000円 |
例3:25年5月1日に、リース会社と自動車のリース契約(リース期間3年、年間リース料120,000円、リース料の支払いは毎年4月30日に当座預金から振込、オペレーティング・リースに該当)の場合
・25年5月1日:
<仕訳なし>
・26年3月31日:
| 借方 | 貸方 |
| 支払リース料 110,000円 | 未払リース料 110,000円 |
・26年4月1日(再振替仕訳):
| 借方 | 貸方 |
| 未払リース料 110,000円 | 支払リース料 110,000円 |
・26年4月30日:
| 借方 | 貸方 |
| 支払リース料 120,000円 | 当座預金 120,000円 |
※以降毎年同様の仕訳を行う
#「ファイナンス・リース」の会計処理
ファイナンス・リースで借りた物は、借金をして購入したも同然であるため、固定資産に計上し減価償却で費用計上していく必要があります。このようにリース契約で借りた物を「借主が資産計上」する処理を、会計上では「売買処理」と呼びます。
2級では、「利子抜き法」と「利子込み法」の2種類の会計処理を学びます。勘定科目は「リース資産」と「リース債務」を使用し、「リース実行時」に計上します。減価償却は「耐用年数をリース期間とし、残存価額を0」とする「リース期間定額法」で償却します。
*仕訳の具体例
①利子抜き法
例:資材運搬用に、4,500,000円のトラックを毎年1,000,000円のリース料で5年のファイナンス・リース契約をした場合(利息は合計500,000円で、年間100,000円となる。)
・リース実行時
| 借方 | 貸方 |
| リース資産 4,500,000円 | リース債務 4,500,000円 |
・リース料支払い時
| 借方 | 貸方 |
| リース債務 900,000円 | 当座預金 1,000,000円 |
| 支払利息 100,000円 |
・決算日
| 借方 | 貸方 |
| 減価償却費 900,000円 | リース資産減価償却累計額 900,000円 |
②利子込み法
例:資材運搬用に、4,500,000円のトラックを毎年1,000,000円のリース料で5年のファイナンス・リース契約をした場合(利息は合計500,000円で、利息も資産・債務に含める。)
・リース実行時
| 借方 | 貸方 |
| リース資産 5,000,000円 | リース債務 5,000,000円 |
・リース料支払い時
| 借方 | 貸方 |
| リース債務 1,000,000円 | 当座預金 1,000,000円 |
・決算日
| 借方 | 貸方 |
| 減価償却費 1,000,000円 | リース資産減価償却累計額 1,000,000円 |
「ファイナンス・リース」の分類(補足)
利子抜き法や利子込み法などの簡便法を使用できるのは、諸条件を全て満たす場合のみです。条件は、①中小企業である、②所有権移転外ファイナンス・リース取引である、③リース契約の重要性が高い(リース料が300万円超など)、④原則法を用いるほど厳密な会計が求められていないor実務負担が大きすぎる、があります。(下表参照)

「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画は こちらからどうぞ「リース取引の解説」
※初めての方は、こちらの記事から読んでいただけますと、幸いです。