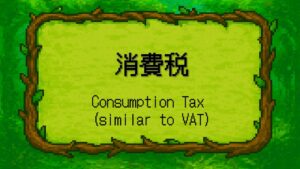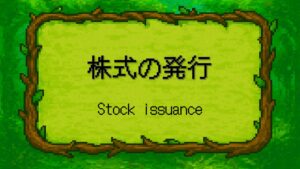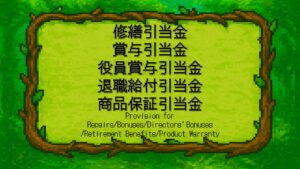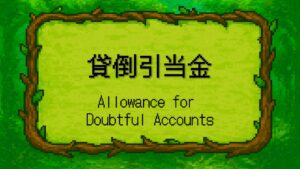はじめに
この記事では、以下の3つの項目を復習・整理することを目標にしています。
①有形固定資産の減価償却法(定額法・定率法・生産高比例法・200%定率法)
②有形固定資産の除却・売却・廃棄
③建物仮勘定/資本的支出・収益的支出/火災滅失時の会計処理
それでは、よろしくお願いします。(※使用教材の第6章「有形固定資産」を参考に作成しています。)
有形固定資産の減価償却法
#有形固定資産とは
有形固定資産とは、「長期にわたり使用する資産で、姿・形があるもの」を指し、「土地、建物、備品、自動車(車両運搬具)」などが該当します。また、減価償却の対象(「土地」は対象外)になります。他の固定資産(無形固定資産/投資その他の資産)との比較は、以下の表を参照してください。
| 固定資産分類 | 内容 | 具体例 | 備考 |
| 有形固定資産 | 形があり、長期的に使用する資産 | 土地、建物、車両、機械、備品 | 「減価償却」の対象(土地は除く) |
| 無形固定資産 | 形はないが、長期的に利用する資産 | ソフトウェア、特許権、商標権、のれん | 「償却」の対象 |
| 投資その他の資産 | 上記2つに分類されない資産 | 満期保有目的債権、子会社株式、長期貸付金 | 評価損処理あり |
#減価償却とは
減価償却とは、「資産の価値を使用年数・使用量に応じて分割し、毎年費用処理する」ことを指します。方法は、帳簿上の処理方法と計算方法で分かれています。また、減価償却の仕訳は、決算時に行われます。
帳簿上の処理方法
「直接法」と「間接法」の2種類があります。
| 方法 | 内容 |
| 直接法 | 「減価償却費」を「固定資産」から差し引いて、取得金額を直接減少させる |
| 間接法 | 「減価償却費」を「減価償却累計額」で管理し、「固定資産」は取得金額のまま表示 |
計算方法
「定額法」と「定率法」と「生産高比例法」の3種類が、簿記2級で出題される会計ルール上の計算方法です。
| 計算方法 | 内容 | 特徴 |
| 定額法 | 毎年一定額を費用に計上する方法 | 各年の償却費が同額で、計画的に償却される |
| 定率法 | 毎年一定率を帳簿価額にかけて償却する方法 | 初年度の償却費が多く、年々減っていく |
| 生産高比例法 | 使用量や生産量に比例して償却する方法 | 機械など使用度合に応じた償却ができる |
定額法
毎期、一定額ずつ減価償却費を計上する方法です。
(取得価額-残存価額)÷耐用年数=減価償却費
例1:取得金額:500,000円、残存価額:50,000円、耐用年数:5年の場合
毎期の減価償却費は、(500,000-50,000)÷5=90,000円となる。
例2:例1と同様の有形固定資産を、12月10日取得した場合の決算整理仕訳(3月31日決算)
期中取得したら、減価償却費は月割(取得月含む)になるので、12・1・2・3月の4ヶ月分を減価償却費に計上する。
よって、取得年の減価償却費は、90,000×4/12(1/3)=30,000円となる。
定率法
毎期、帳簿価額(未償却残高)に一定割合(償却率)をかけて減価償却費を計算する方法です。(年度が進むにつれて減価償却費が少なくなる特徴があります。)
(取得価額 − 期首減価償却累計額)×償却率=期首時点の未償却残高×償却率=減価償却費
例1:取得金額:500,000円、残存価額:50,000円、耐用年数:5年、償却率:0.36904の場合
・1年目の減価償却費は、500,000×0.36904=184,520円となる。
・2年目の減価償却費は、(500,000−184,520)×0.36904=116,425円となる。(期首償却残高は、315480円)
・3年目の減価償却費は、(315,480−116,425)×0.36904=73,459円となる。(期首償却残高は、199,055円)
・4年目の減価償却費は、(199,055−73,459)×0.36904=46,350円となる。(期首償却残高は、125,596円)
・5年目の減価償却費は、(125,596−46,350)×0.36904=29,245円となり、(残存価額:50,000円のため)調整後、29,246円となる。(期首償却残高は、79,246円)
償却率自体が残存価額を考慮して設定されている率であるため、定率法では残存価額を考慮して減価償却費を算出しません。
例2:例1と同様の有形固定資産を、12月10日取得した場合の決算整理仕訳(3月31日決算)
期中取得したら、減価償却費は月割(取得月含む)になるので、12・1・2・3月の4ヶ月分を減価償却費に計上する。よって、取得年の減価償却費は、(500,000−0)×0.36904×4/12(1/3)=61,507円となる。
生産高比例法
毎期、実際の使用量や生産量に応じて減価償却費を計算する方法です。生産量や走行距離などに比例して費用配分します。
(取得価額 − 残存価額)×実際使用量/見積総使用量=減価償却費
例:取得金額:500,000円、残存価額:50,000円、耐用年数:5年、走行可能な見積総距離:9万kmの自動車を購入した場合
・1年目(3万km走行)の減価償却費は、(500,000−50,000)×3/9(1/3)=150,000円となる。
・2年目(1万km走行)の減価償却費は、(500,000−50,000)×1/9=50,000円となる。
期中取得の場合でも、使用しなければ、減価償却費の計上は発生しません。
200%定率法
定額法の2倍(=200%)の償却率で減価償却費を計上する方法です。償却率は、「200%÷耐用年数」で求めます。
毎期、①「未償却残高に償却率を乗じた減価償却費」と②「取得価額に保証率を乗じた償却保証額」を比較し、「①」が大きい場合は「①の金額」を、「②」が大きい場合は「未償却残高×償却率の金額」を減価償却費として計上する方法です。
この計算方法は、法人税法上のオリジナルルールであり、会計理論は存在しません。(丸暗記するしかないです。)
例:取得金額:500,000円、残存価額:0円、耐用年数:5年、保証率:0.108、改定償却率:0.500とした場合
償却率は40%(200%÷5)で、償却保証額は500,000×0.108=54,000円となります。
・1年目の減価償却費は、500,000×0.4=200,000円(>54,000円)となる。
・2年目の減価償却費は、(500,000-200,000)×0.4=120,000円(>54,000円)となる。
・3年目の減価償却費は、(300,000-120,000)×0.4=72,000円(>54,000円)となる。
・4年目の減価償却費は、(180,000-72,000)×0.4=43,200円(<54,000円)であるため、54,000円となる。
・5年目の減価償却費は、4年目と同様に、54,000円(108,000-54,000)となる。
これで、残存価額0円となる。
有形固定資産の除却・売却・廃棄
#検定試験での除却・売却・廃棄とは
検定試験では、除却・売却・廃棄は、以下の表の意味で通常使用されている。「除却」は、税務上では「資産を使用しなくなった=事業用途から外した」という意味で、会計上では「固定資産台帳から除く処理をした」という意味で使用されており、混同しやすいので注意が必要です。売却・廃棄を行えば、会計上の「除却」は必ず行われます。
| 用語 | 試験での意味 |
| 除却 | スクラップとして売却することを予定して(会計上の)除却すること |
| 売却 | (税務上の)除却せずそのまま売却すること |
| 廃棄 | (税務上の)除却せずそのまま廃棄すること |
#「除却」の仕訳
例:所有している自動車(取得価額1,000,000円、減価償却累計額800,000円)を除却した。スクラップとしては100,000円の処分可能価額がある場合(貯蔵品は、実際に売却したら未収入金(現金)などに振り替える。)
| 借方 | 貸方 |
| 車両運搬具減価償却累計額 800,000円 | 車両運搬具 1,000,000円 |
| 貯蔵品 100,000円 | |
| 固定資産除却損 100,000円 |
#「売却」の仕訳
例:所有している自動車(取得価額1,000,000円、減価償却累計額800,000円)を150,000円で売却した。150,000円は現金で受け取った場合
| 借方 | 貸方 |
| 車両運搬具減価償却累計額 800,000円 | 車両運搬具 1,000,000円 |
| 現金 150,000円 | |
| 固定資産売却損 50,000円 |
#「廃棄」の仕訳
例:所有している自動車(取得価額1,000,000円、減価償却累計額800,000円)を廃棄した。廃棄費用の50,000円は現金で支払った場合
| 借方 | 貸方 |
| 車両運搬具減価償却累計額 800,000円 | 車両運搬具 1,000,000円 |
| 固定資産廃棄損 250,000円 | 現金 50,000円 |
#期中仕訳(応用)
例:25年6月10日に所有している機械(24年4月20日購入、取得価額1,000,000円、残存価額100,000円、耐用年数5年、定率法、償却率0.36904、間接法)を800,000円で売却し、現金で受け取った場合
・25年3月31日までの減価償却費:1,000,000×0.36904=369,040円
・25年6月10日までの減価償却費:(1,000,000ー369,040)×0.36904×3/12=58,212円
| 借方 | 貸方 |
| 機械装置減価償却累計額 369,040円 | 機械装置 1,000,000円 |
| 減価償却費 58,212円 | 固定資産売却益 227,252円 |
| 現金 800,000円 |
その他の論点
#建設仮勘定について
有形固定資産を建設中のときに使用する一時的な資産勘定。工事が完了するまでは固定資産にできないため、「仮に積み立てておく」ための勘定科目。
例:
・建物(5,000,000円)の建設にあたり、建設業者に手付金(1,000,000円)の小切手を振り出した
| 借方 | 貸方 |
| 建物仮勘定 1,000,000円 | 当座預金 1,000,000円 |
・2回目の支払いで、建設業者に手付金(1,000,000円)の小切手を振り出した
| 借方 | 貸方 |
| 建物仮勘定 1,000,000円 | 当座預金 1,000,000円 |
・建物が完成し、建設業者に残金(3,000,000円)の小切手を振り出し、建物の引き渡しを受けた
| 借方 | 貸方 |
| 建物 5,000,000円 | 当座預金 3,000,000円 |
| 建物仮勘定 2,000,000円 |
#「資本的支出」と「収益的支出」について
資産の価値を増加させたり、寿命を延ばす支出(建物の増築・耐震強度増加)を「資本的支出」、資産の維持・修繕など通常の運用維持のための支出(建物の水漏れ修理や外壁塗装)を「収益的支出」という。
例1:建物の改良と修繕を行い、支払いは小切手(1,000,000円)を振り出した。この内、300,000円は改良と認められた場合。
| 借方 | 貸方 |
| 建物 300,000円 | 当座預金 1,000,000円 |
| 修繕費 700,000円 |
例2:建物を増設中(工事代金5,000,000円はかねてから支払済)。工事が終了し、引き渡しを受け、代金のうち2,000,000円が修繕費として使用されていた場合
| 借方 | 貸方 |
| 建物 3,000,000円 | 建物仮勘定 5,000,000円 |
| 修繕費 2,000,000円 |
#固定資産が火災で滅失した場合
例1:建物(取得金額:1,000,000円、減価償却累計額:700,000円)が火災により焼失した場合
| 借方 | 貸方 |
| 建物減価償却累計額 700,000円 | 建物 1,000,000円 |
| 火災損失 300,000円 |
例2:
・建物(取得金額:1,000,000円、減価償却累計額:700,000円)が火災により焼失した。限度額1,000,000円の火災保険がかけられている。
| 借方 | 貸方 |
| 建物減価償却累計額 700,000円 | 建物 1,000,000円 |
| 未決算 300,000円 |
・後日、保険会社より保険金1,000,000円を支払う旨の連絡が入った。
| 借方 | 貸方 |
| 未収入金 1,000,000円 | 未決算 300,000円 |
| 保険差益 700,000円 |
例3:
・建物(取得金額:1,000,000円、減価償却累計額:700,000円)が火災により焼失した。限度額1,000,000円の火災保険がかけられている。
| 借方 | 貸方 |
| 建物減価償却累計額 700,000円 | 建物 1,000,000円 |
| 未決算 300,000円 |
・後日、保険会社より保険金200,000円を支払う旨の連絡が入った。
| 借方 | 貸方 |
| 未収入金 200,000円 | 未決算 300,000円 |
| 火災損失 100,000円 |
①「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画は こちらからどうぞ「定率法・生産高比例法・除却/売却/廃棄」
②「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画は こちらからどうぞ「その他の論点」
③「ふくしままさゆき」さんのYouTube解説動画は こちらからどうぞ「200%定率法」(視聴には、別途メンバーシップ登録が必要です。)
※初めての方は、こちらの記事から読んでいただけますと幸いです。